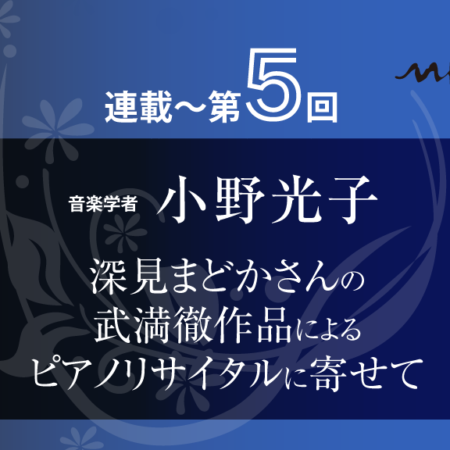連載第6回目(全14回掲載予定)
そろそろ武満のピアノ作品にまつわる話に移りたい。まずは武満18歳のときの、おそらく生前未発表の《ロマンス》。
この曲は「1949年6月26日」の日付で恩師・清瀬保二と友人・鈴木博義宛に清書された楽譜がそれぞれ残されている。武満の没後である1998年10月14日に紀尾井ホールで行われた「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」で藤井一興さんによる演奏が初演になるかもしれない。
楽譜の冒頭には「Adagio sostenuto, nobile e funebre」とある。訳すと「ゆっくりと音を保って、気高く悲しみをもって」となろうか。ここにすでに武満の特徴が表れている。気高さと悲しみはその後の作品に通底し、ソステヌートは音楽的な表現の中で磨かれてゆく。
「アダージョ・ソステヌート」といえばベートーヴェンのソナタ《月光》やラフマニノフの《ピアノ協奏曲第2番》の第2楽章を思い起こす人も多いと思う。このゆっくりとたゆとうテンポに武満は試行錯誤の上にたどり着いた。ベートーヴェンがこの曲を聴いたらどう思うだろうか。武満は作曲をし始めた頃を回顧して「ベートーヴェンの音楽は“生”の深いところで私を鼓舞し続けるが私の肉体としての音感は、実際にはベートーヴェンの音楽からは遠くかけ離れたものであった」と書いている。逆にベートーヴェンからしたら武満の音感は遠クカケ離レテマスネ、と言うかもしれない。

《ロマンス》は冒頭、一音で始まる。歌うようなメロディーに5音音階が響くのはこの時期ならではだが、そこに無理に和声を付けようとしていない。ソステヌート(音を保って)で奏することは一つの答えだったのではないか。鍵盤を打った瞬間の雑音がなくなり余韻が安定したときの響きの美しさがそこで生じる。曲は次第に感情が高まるかのようにフォルティッシモに達したあと冒頭のメロディーが再び登場し、だんだん静かに遅くなって終わる。
《ロマンス》を書いたのち武満は清瀬の所属する「新作曲派協会」に正式に入会し、一人の作曲家として扱われる存在になった。そこでは明治生まれの清瀬や松平頼則、大正生まれの早坂文雄のような人が所属し、会合を開いて意見を交わしながら日本人としてのオリジナルな創作を模索し発表の会を設けていた。若い武満は「新作曲派協会」だけでは飽き足らず、進駐軍の設立したCIE図書館や美術家の集いへと足繁く通い、交友関係を広げていた。武満さんは内省的なところがあると同時に社交的なところがある。そしてこの行動力と内省さで武満さんはその後、広く深く日本の文化を探究しながら欧米の文化、同時代の国内外のアートへも視野を広げて創作の根を太く確かなものとしてゆく。《ロマンス》はその始まりに位置する作品だ。
【参考文献】
武満徹「わが思索 わが風土〈四〉」『朝日新聞』1971年10月21日付夕刊
(『樹の鏡、草原の鏡』『武満徹著作集第1巻』所収)。